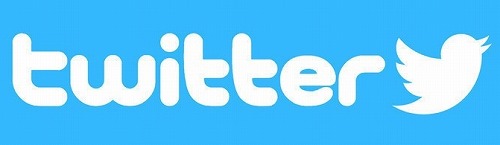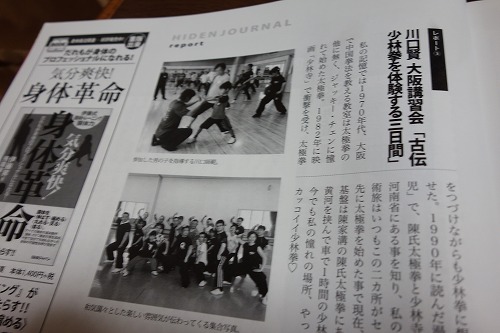磨溝物語
- 2018/01/26 10:54
- カテゴリー:武術
先日「秘伝」誌に掲載された「古伝少林拳の故郷を訪ねる旅路 今こそ蘇る磨溝の拳」について。誌面の都合で泣く泣く削った部分が多々あり。この磨溝の名前の由来についてもその一部分です。
以前mixiに投稿したものですが、改めて。
磨溝にはこうした故事のある旧跡が数多く遺っています。今後はこれらの故事や古い言い伝え、習慣なども少しずつ整理していこうと思っています。
●磨溝の名前の由来
現在我々が生きている天地が開闢する以前、この付近には桑桑、昌昌という双子の姉弟が住んでいました。二人が十六歳の時、母は病気で亡くなり、それ以後は父が畑を耕し、桑桑は家事を行い、昌昌は毎日学校に通って暮らしていました。
ある時昌昌が学校から家に帰る途中、ふいに背後より名前を呼ぶ声があり、振り返るとそれはこの路にには古くよりある雌雄二頭の石で出来た虎でした。石虎いわく「腹が減って仕方がない、お前が明日学校に行くときに、饅頭を持って来て食べさせてはくれまいか」と。
その次の日より昌昌は毎日朝ご飯を食べると余分に饅頭と持って出かけ、途中で石虎にそれを食べさせました。姉の桑桑は弟が毎日余分に饅頭を持って出るのを不思議に思い、それを問うたので、昌昌はありのままを姉に伝えました。桑桑は「これにはきっと何か奥深い意味があるに違いない」と考え、次の日からは二頭の石虎それぞれに食べさせるように、二つの饅頭を弟に持たせて出しました。
こうして九十九日が経ったある日、石虎が昌昌に言いました。
「明日の午後、お前と姉の二人でここに来なさい。決して忘れないように」
次の日、姉弟二人が石虎の前に着くと、突然天が暗転し、山地がぐらぐらと揺れ始めました。すると雌雄の石虎は昌昌と桑桑とをそれぞれ一口で飲み込みその腹に納めました。姉弟が石虎に問うても、石虎は「天機を口外することは出来ない」と語らず、二人はただ石虎の外で天が倒壊し、山が崩れ、地が陥没する音を聞くばかり。石虎の腹の中でこれまで自分たちが持ってきた饅頭を食べながら、こうして百日が過ぎた時、石虎は口を開いて言いました。
「天地は開闢した、お前達二人は出てきなさい」
姉弟二人が外に出てみると、世界には何もなくなっていました。ここで石虎は二人に真実を告げました。「お前達が我々の腹で過ごした一日は外界の一万年に相当する。今は大難が去り、天地が開闢し、新しい世界が始まったのだ」と。
二人は自分たちはこの石虎のお陰で大災厄を避ける事ができたと知り、急いでこの神虎の前に跪き叩頭をすると、石虎は二人に「現在の世界にはお前達二人しか残っていない」と告げ、二人に結婚して後代子孫を残すように勧めました。しかし二人は血の繋がった姉弟ですから、涙を流してそれは出来ないと訴えたので、ある日神虎は桑桑の夢に出現し「東西の山頂から石臼を転がし、中間の溝で見事臼が合体すれば、結婚するがよかろう」と告げました。
姉弟は神虎の言う通り、桑桑が西の山に、昌昌が東の山に登り、そこからそれぞれ石臼を転がすと、石臼の凹凸は二人の中間で「がしゃん」と音を立て、計ったように一つになったので、姉弟は天地を拝して婚姻を結び、子孫を残すことに決めました。現在の世界の人類は皆この桑桑、昌昌の子孫であり、実はこの二人は女媧と伏羲であるとも言われています。磨溝の名前は二人がこの溝で磨(臼)を転がし、婚姻を決めたたという故事から来ているのです。